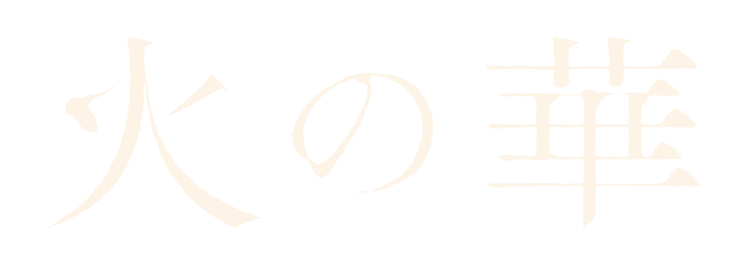【イベントレポート】名タッグここにあり!主演:山本一賢×監督:小島央大監督×ゲスト:森直人(映画評論家)
10月8日(水)に開催された、公開前の映画『火の華』特別試写会。上映後に、共同で企画・脚本に名を連ねる、主演の山本一賢さんと小島央大監督、そして映画評論家の森直人さんを聞き手にお招きし、トークイベントを行いました。製作に至るまでの経緯、2人での脚本執筆、本作で描かれるテーマ、撮影中のエピソードなど徹底解説!

花火と自衛隊の世界がいかに交わったのか、企画の成り立ち
森 直人(以下、森)「大変な力作で感服いたしました。日本ではなかなかないタイプの映画。お互いの長編デビュー作でもありました、2021年の『JOINT』に続いてのタッグですね。今回は共同で企画を立て、脚本も書かれていますが、どういった経緯でこの企画が始まったのでしょうか」
小島央大監督(以下、小島)「僕はもともと花火が好きで、花火大会で花火は見えますが、それを打ち上げている人がどこにいるのか、どんな人が上げているのかは見えず、ミステリアス。花火職人に何かストーリーがあるなと予感をしていたので、映画化できたらすごく面白いんじゃないかと。『JOINT』の興行が落ち着いて、山本さんとまた撮ろうという話をしている中で、山本さんは花火職人に合うんじゃないかなと思ったんです」
森「花火が始まりだったんですね。ところが、そこから2016年の自衛隊日報問題もモチーフとなっています。PKO(国連平和維持活動)のために南スーダンに派遣された自衛隊部隊が作成した日報が隠蔽された問題です。日報問題と花火師のお話はどのように結びついたのですか」
小島「山本さんと話している中で、何者かが花火師になっていくという過程をストーリーにするのがいいなと思ったんです。最初は、江戸っ子やヤクザの息子が花火職人に目覚めるとか、色々設定があったんですが、花火や火薬の歴史、日本の花火が持つ精神性をリサーチしていく中で、“戦争”や“平和”と密接に繋がっているものだというのが分かってきて。戦のない江戸時代に武家は暇だから、大砲を横に向けて花火を打ち上げていたというのが、打ち上げ花火の原点なんです。兵士が花火師になるというストーリーが元々あったんだなと。その物語を現代劇としてやりたいなとなった時に、自衛隊は戦争をしているわけではないんですけど、調べていくと、戦闘に限りなく近い状態が現実にあって、実際に映画にあるようなこともあり得るんじゃないかなというのが始まりです」
森「山本さん、最初の花火師のお話から聞くと、踏み込む覚悟がいりますよね」
山本一賢(以下、山本)「もちろん覚悟はあって、どんな話でもやるつもりでした。面白かったのは、花火師になるという話は決まっていて、もともと花火師の人が火薬を持ち出して薬莢に詰めて売っている奴がいるという事を聞いたんですよ。それが面白いという話を央大としていて、そこから央大が広げて、そこに自衛隊の話も混ぜてたらやりたいことがいっぱい増えちゃって(笑)」
森「確かに同じ“火薬”を使いますが、平和利用なのか、それが戦闘のものになるのか。どちらも“火薬”から派生するけど、全く逆の方向を向くのが“花火”と“戦争”。自衛隊が海外で活動できるというのは、基本的には非戦闘地域に限定されていますが、日報の中では“戦闘”という文言が使用されていたことが問題になりました。自衛隊が危険な地域に派遣されているのではないか、それがいわゆる憲法9条に反するのではないか。PTSDの問題も日本ではないものとしてされているというところに、この映画は踏み込んだところに大きな回路が出てきたなと思うんですが、こうした物語はどのように組み立てられましたか」
小島「何者かが花火師になるという話の中で、花火を見た時に美しいと感じることがどういうことなのか。自衛隊でもし戦闘が起きて、PTSDになった主人公は、どのようにして花火にたどり着けるだろうか。花火が自分の人生を救ってくれるものだと気付き始めるところまでにいろんな障害物や、自身の中に障害物があったり、仲間が闇の方に引っ張っていこうとしたり、それらを色々と想像していきました」
脚本づくりと役づくり、新潟と海外での撮影
森「お二人の脚本づくりは、キャッチボールのように1年ぐらいかけて作っていったとおっしゃっていましたけれども、山本さんが演じられた主人公・島田の人物像はどのように作られたのですか」
小島「山本さんが一人称で脚本を書いていて、僕は三人称で書いていました。それを交換日記のように情報を循環させながら、だんだん核心に迫っていくみたいなプロセスでした」
山本「僕は日記みたく書いていました。こういうことがあってこういう気持ちになったとか、こんなはずじゃなかったとか、酒がやめられない、どうしようとか」
森「ご自身の生っぽい感情も島田には混ざってきたりもしましたか」
山本「すごいしましたね。島田に侵食されそうになって困ってました」
森「冒頭の南スーダンでの戦闘シーンでは、図らずも少年兵を撃ち殺してしまう。その大きなトラウマをご自身の中に重石として設定して、その役を生きてみようという過程だったということですよね」
山本「そうですね。しんどいし友達が減りますよね(笑)。お前変わったな、と言われたり」
森「私生活にも影響が出るぐらいにのめり込んでいたんですね。そこから、小島監督が物語を肉付けしていったのでしょうか。かなり変わった組み立て方のような気がします」
小島「島田の悩みや葛藤が掻き乱されながら、それでも光に寄り添いたい、救いがあるという終わりにはしたかったので、どんどん負荷をかけていって…」
山本「央大は僕を苦しめたいわけですよ(笑)。途中で精神が崩壊しちゃって、“お前は悪魔だ!”みたいなことを泣きながら言った覚えがあります。それなのに、すごい嬉しそうにしていて…」
小島「仕上がってきたと思いましたね。二人で書いてるので、僕だけの責任じゃないなと(笑)」
森「お2人は、面白い関係ですね(笑)。脚本の作り方も面白いです。『火の華』で島田が武器ビジネスに関わって抜けられないというのは、『JOINT』からの繋がりも感じます。『JOINT』は、日本の裏ビジネスの総目録のような、かなりドキュメンタルな要素が強かったと思いますけれども、その流れを『火の華』にも導入していったというところはありますか」
小島監督「繋げようとは思ってはいなかったんですが、(島田が抱える)とてつもないトラウマと、PTSDという病症をキャラクターの中に設定して、また舞台となった新潟は花火が盛んな場所であるのと同時に、日本海に面していて犯罪の密輸の入り口となっていて、“火薬”の持つ両面性が表れていて、その場所に島田が存在していているという設定が(『JOINT』からの繋がりを)引き出したかなと思います」
森「新潟を舞台にしたのには、どういった流れがあったのでしょうか」
小島「最初は江戸っ子の話にしようとしていたんですが、実際には東京で花火は作られていなくて。密集地だと危険なので許可が下りない。そこで日本の中の規模感で言うと、やっぱり長岡が一番、世界一の花火大会なんじゃないかなと。実際に見た時にもちろん感動もしたんですが、長岡空襲の慰霊が込められていて、そして元々花火が根付いている地域なので、人が亡くなられた時や、結婚や赤ん坊が生まれた時も、花火が打ち上げられるという距離感に、一種のカルチャーショックを受けて、新潟を舞台にすることに決めました」
森「長岡空襲が起こったのは、1945年8月1日。大林宣彦監督は『この空の花 長岡花火物語』を2012年に作られましたけど、『火の華』もそういった部分が映画の大きな意味を持って肉付けされ、出来上がったんですね。撮影はいつ頃行われましたか」
小島「2023年の8月24日の(新潟県)小千谷市での花火大会からです。その前に長岡花火でも撮影したんですが、それはインサートで、島田が花火を見てPTSDを発症するシーンの撮影が正式なクランクインです。実際に花火大会の打ち上げ現場に入らせてもらって撮影しました」
森「南スーダンのシーンは、タイで撮影されているんですよね。海外での撮影でご苦労されたことはありますか」
山本「装備された自衛隊の制服を着ていたので、とにかく暑かった。あと海外行って島田が変わるわけですよ。病んでいる島田を先に新潟で撮影していて、体重も12キロぐらい落として、その2か月後にタイでの撮影で、その間に12キロ増やして…」
森「完全にメソッド演技法ですよね。本当にその役を生きて、近づいていかれている。最初『JOINT』の主人公と別人かと思いましたもん」
「PTSD」を描くということ
森「この映画の重要な主題となるのが、PTSDですね。僕が思い浮かんだのは、2014年クリント・イーストウッド監督の『アメリカン・スナイパー』。イラク戦争に従事した実際の狙撃兵をモデルにした映画です。それまでにも『タクシードライバー』や『ランボー』、『ディア・ハンター』など、ベトナム戦争時のPTSDを扱った映画も多く存在していますが、日本だと自衛官のPTSDというものは原理的に法的ないものとされているので、この題材に踏み込まれたのは、本当にすごいなと思うんです。リサーチや取材はされながらも、物語はあくまでフィクションですよね。そのバランスはどのように取られたのでしょうか」
小島「日本でもPTSDを研究されている方がいて、震災当時の自衛官が実際PTSDを抱えている方など、実際ストレスによる病症というのは確実にあるんです。それに対する対策や、じゃあ本当に戦争が起きた場合どうするかということも研究されている方や、元自衛官の方にも派遣された時の事だったり、山本さんと一緒に話を伺いました。日本での情報はすごく少ないんですけど、なるべく実話や実録を引き出して、あとはアメリカのケースにはなってしまうんですが、PTSDがどのように症状として現れるかは個人によって変わってくるんですけど、島田の場合はどのように表れていくか、例えばどのように話すか、どのように目つきが変わったり、何が好きで何が嫌いで、何に反応して反応しないのかと。これが島田らしいと、少しずつ山本さんと話しながら組み立てていきました」
森「山本さんはご自身の肉体を持って、その痛みを感じていくという体験をされていったのでしょうか。映画の中で、花火の打ち上げでPTSDを発症する描写がありますが、想像だけではなかなか演じることができないなと」
山本「そう言うと大げさですけど、先に身体が反応するように作っていました」
森「『JOINT』と『火の華』どちらを観ても、現実性へのアプローチに手を抜いていないことがわかります。あと僕が思うのは、アメリカ映画が普通にやっていることを日本という土壌の中で、リアルな現実を踏まえながら小島監督がやろうとしているんじゃないかと」
小島「意識はしていませんが、アメリカに10年住んでいたので、週1は映画館に通い、Netflixがまだ始まったばかりの、DVDレンタル時代から利用して、毎日2、3本分くらい映画を観てました。そういった環境は、確実に影響しているなとは思います」
森「その中で日本映画が扱う社会的題材ですとか、ポリティカルなものというのはいかがですか。ちょっとアメリカ映画というものが扱っているものに対しては、及び腰っていうのは変かもしれないですが、距離があるように感じたりはしていましたか?」
小島「もちろんハリウッドらしいPTSDの描き方や、ヨーロッパっぽい描き方とか、それぞれ主流だったり雰囲気があると思うんですけど、それはあんまり意識していなくて。本当に島田に寄り添った形で表現できたらなと思ってました」
森「そろそろ時間ということで、最後にお互いにどういった存在ですか」
小島「映画の芯を作る人ですね。本当にこの島田という主人公はどれだけ芯があって、それが映画の核になるかな、それを本当に任せられる人だと思ってます」
山本「なんでもできる、映画制作アプリみたいな(笑)。インストールすると色々やってくれる。天才ってよく言われているけど、すごい努力家なんですよね。意外とこう見えて土臭い」
森「お二人は名タッグだと思います。本日はありがとうございました」